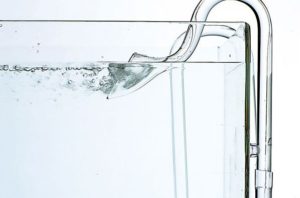日本の平均的な水道水の水質は、弱アルカリ性/中硬度と言われています。
多くの水草や熱帯魚にとって最適な水質は、弱酸性/低硬度となりますので、水質の差に悩んでる人も多いです。
水質がアルカリに偏ると
- コケが発生しやすくなる
- アンモニアが有害になる
- 水草のCO2利用率が下がる
- 水草の栄養吸収の効率が下がる
以上のようなデメリットがあり、特に水草水槽において、pHは弱酸性を保った方が良いとされています。
ということで今回は水槽のpHを下げる方法や、低く保つ方法を紹介したいと思います。
低床にソイルを使う
低床をソイルにすると、ソイルのイオン交換によって、弱酸性の軟水にしてくれます。
どのくらいpHを下がるかは商品によって変わりますが、、6.0~6.5程度になる場合が多いです。
ソイルのpH降下作用は大体3ヶ月程度で無くなりますが、その頃には水槽内の硝化作用が働いてpHが下がる傾向があります。
具体的に言うと、ろ過バクテリアがアンモニアや亜硝酸を分解する過程で発生する、水素イオンや硝酸塩によって、pHを酸性に傾けます。
簡単に言えば、立ち上げから時間が経つにつれ、水槽の水は徐々に酸性に傾いていく傾向があるということです。
水換えを頻繁に行うと水道水の水質=水槽内に近くなるので、上記の法則には当てはまらないこともあります。水道水の硬度が高ければ、水換えの度に硬度が高くなっていきます。
水質調整剤を使う
水質調整剤はpHを強制的に下げる添加剤です。
中でも「テトラPH/KHマイナス」は長年、使用されてきた定番用品です。
現状、最も簡単にpHを下げる方法ですが、水槽と水道水のpHを確実に測定し、微調整しながら使用する必要があります。
規定量は10リットルに2mlで、大体pHを1-1.5程度下げてくれます。
また、水槽に直接、添加するのではなく、水換えに使用する水道水を調節する方がリスクが少ないです。
もし水槽内に砂利や竜王石などの硬度を上げる材料が入っている場合、この調整剤は使用しない方が良いです。石等に含まれるミネラル分が溶け込んでしまい、結果的にpHが上昇してしまう可能性がある為です。また、主成分は硫酸・塩酸のため、取り扱いには十分、注意して下さい。
パワーハウス ソフトタイプを使う
パワーハウスはフィルターの高性能ろ材のことで昔から評価が高いろ材です。
パワーハウスのソフトタイプはpHを少し下げてくれる作用があるので、水草水槽には重宝します。
やや高価ですがpH調節機能だけではなく、生物ろ材としても非常に優秀なので、非常に評価が高いろ材です。
ちなみにpHを下げる力は0.2~0.3程で、効果の持続期間は1年~1年半程度です。
リバースグレイン ソフトを使用する
リバースグレイン ソフトはフィルターの中に入れるタイプの水質調整剤です。
何回か使用経験がありますが、うたい文句通りの水質pH6.8、GH/KHを1前後に保ってくれます。
またコケの抑制効果もあり、ろ材としての役割も果たし、水質安定化に貢献します。
リバースグレイン ソフトは酸化物を加えるのではなく、アルカリ性分を吸着する仕組みなので、安全性も高いです。
ピートモスのように水を茶色くしてしまうこともありません。
デメリットはランニングコストがかかることで、環境差はありますが、三か月に一回の交換が目安です。
ピートモスを使用する
ピートモスやパミスを使用してpHを下げる方法も定番です。
上記の「エーハイムトーフ ペレット」はその中でも一番使いやすい商品なのでオススメです。
使い方は付属のネットに入れてフィルターに入れるだけ。
効果は3~6週間持続しますがpH降下作用が結構強いので、規定量は使わず、まずは少量で試しpHを確認した方がいいです。
デメリットは飼育水が茶色っぽくなることです。
また、この際に活性炭を入れてしまうと、pH降下の能力が相殺されてしまうので、活性炭の使用も出来ません。
浄水器を使用する
浄水器を使用して、水道水の水質を調整する方法です。
ただし、通常の浄水では塩素を除去するだけなので、硬度を下げたい場合は、別途カチオンフィルターの接続が必要となります。
特に大量の水を扱う大型水槽の水換えで浄水器は、非常に有効ですが、初期コストや保管スペースの問題があります。
メーカーにもよりますが、カチオンフィルターを合わせ大体2万円程度の初期コストがかかります。
カチオンフィルターを通しても、pHの変動はほぼありませんが、カルシウムとマグネシウムといった水中のアルカリ度を高める要素を取り込みますので、結果的に飼育水のpH上昇を抑えることが出来ます。
pHが上がる原因を考える
最後にpHを上げる主な原因を紹介します。
砂利系の低床を使用している
特に新品の砂利系の低床はカルシウムやマグネシウムが含まれている場合が多く、基本的にはアルカリ寄りの水質になることが多いです。
時間の経過と共に中性へ近づいていきますが、ソイルを使用すれば最初から弱酸性の水質が実現出来るので、特に水草水槽をやりたい場合はソイルを選択する方が無難です。

レイアウト用の石を多用している

石は種類にもよりますが水槽内のpHと硬度を上昇させます。
竜王石など石の表面に白い結晶が走っている石は、特に硬度が上がりやすい傾向があります。
山谷石や溶岩石など、白い部分がほとんど無く全体的に黒っぽい石は、余り水質に影響を与えません。
特に石組みレイアウト水槽では大きい石を多数配置しますから、そのような水槽だとアルカリ寄りの水質になることが多いです。
その場合は硬度があっても育つ水草(キューバパールグラス等)を選択するのも手です。
カリウム肥料を添加している
特にカリウム液肥を毎日添加している方はpHに注意する必要があります。
カリウム液肥は強いアルカリ性を示しますので添加するとpHに影響が出ます。
やはり理想は添加前と添加後でpHを測定してみることです。
例えば、その前後でpHが0.5程度上がっているならば過剰に添加していることになるので、添加する量を調整する必要があります。
もしくはpHに影響が出ないADAのグリーンブライティ・ニュートラルKを使用する方法もあります。
水換えを頻繁にしている
水道水のpHが高い地域で、水換えを頻繁にしていると、当然、水槽内のpHは水道水に近づくことになります。
水道水の水質は地域や時期によっても大きく異なりますが、日本は中性から弱アルカリ性の地域が多いです。
そのため、水質を弱酸性に保ちたい場合は水換えの際に「テトラPH/KHマイナス」のような水質調整剤を使用するのもオススメです。
まとめ
pHを低く保つ方法を紹介しました。改めてまとめますと
- ソイルを使用する
- 水質調整剤(pH降下剤)を使用する
- ろ材やリバースグレインを使用する
これらを基本にしながら様子を見ると良いと思います。
また、根本的な環境の見直しとして
- 石を水槽内に沢山入れている
- 水道水のpHが高い
- 水換えを沢山している
- 低床に砂利系を使用している
これらをチェックしてみると、水槽内のpHを下げることが出来ると思います。